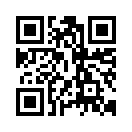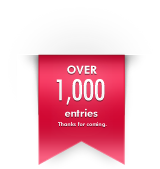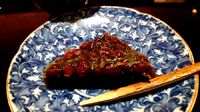■Sublime Text: The text editor you'll fall in love with(公式・英語)
http://www.sublimetext.com/
↑ちなみに Sublime Text を一躍有名にしたのは、
「
The text editor you'll fall in love with(
恋に落ちるテキストエディタ)」
というキャッチコピー。
あまりの使い勝手の良さに離れられなくなるということらしい。
※ちなみに、この後このフレーズが流行して二番煎じがたくさん出たので、これ読んでなるほどと思った人は使わなくていいです。もう2年前くらいからなのでお腹いっぱいです。
またツールが流行するのには時代背景もありまして。
WEB制作の中心は、
インブラウザ・デザインという手法が確立されたからです。
これは WEBデザイナー(笑)や WEB屋(笑)を中心として実行されている制作方法で、Adobe 系のありとあらゆるツールに依存しないようになっています。
過去の制作ワークフローには、グラフィッカーの作る「デザイン案」と呼ばれる画像が必要だったのですが、この部分の制作コストを省略した手法です。
どうやるかというと、ワイヤーフレーム構成案を作った後、いきなりコーディングに入るのです。
これは、CSS3 の表現技術が向上し、ボタンなどを画像で表現する必要が無く、CSS だけで表現できるという時代的な理由もあるのですが。
つまり、どこからかコピーしてきたコード(CSS)を使って構築していけば、誰でも綺麗な「WEBデザイン」ができてしまうということになります。
システムでいえば、オープンソースのライブラリや jQuery を組み合わせたらシステムできちゃった、みたいな感じ?
仕事の矜持によるかもだけど、弊社の
チーフ SE が言うには「そういうのはできてるとは言わない」と力強く言ってます。
当然デザイン業界でもそうですね。
もうひとつの理由は、レスポンシブデザインの台頭。
アダプティブではなく、画面のサイズによって流動的に変化するレスポンシブの概念では、Photoshop や Illustorator という画像制作ツールを使った方法では、手間がかかり効率が悪すぎるのです。
作ってから、書き出して全部のデバイスで画面確認して・・・とか、本気でやろうとしたらかなりのコストがかかります。
これを現地であるブラウザ内で行えば、楽々と制作進行できます。
Sass や
LESS といった CSS を拡張させる技術を使い効率化してしまえば、複数サイトの同時進行とまではいかなくても、連続して次々に制作とかも思いのままです。
インブラウザデザインは、より開発者寄りになっており、最近ではシステム開発者でも綺麗なデザインを作ってくるほど。
何でもできる才能にあふれる人にとっては住みやすい世の中ですね。
能力が低く分業化された企業ではデザイナーとコーダーという職種に分けられていることが多かったのですが、最近ではシステムもフロントエンドエンジニア、バックエンドエンジニアといった職種に分けられることも多いようです。
給料がガクンと下がりそうな感がいいですね!
そういえば旧時代の遺産でいまだに HTML や CSS かけないエンジニアは、もうちょい頑張ってほしい。
(ちなみに昔は「HTMLコーディング」の仕事をどこの部署でやっているかで、その企業の新しいものへの適応能力がどこの部署で発揮されているかが垣間見えました)
またインブラウザによる制作が全て万歳というわけではなく、当然デメリットがあります。
レイアウトやビジュアルが単調で、個性的ではなくなるところです。
これは、制作するのが目的ではなく、結果を出すのが目的の仕事において、かなりの痛手です。
「デザイナー」という職種は、できることを増やして、モノ作りに携わるものとしてのプライドを持ち、より設計や構想といった部分にスキルをあげて他業務と連携していかないと、仕事がなくなっちゃいそうですね。
というわけで、Flash に続いて、Dreamweaver や Photoshop といったツールの存在が世間から潰されてようとしている Adobe の哀しい話なのですが。
ここからもうちょっと続くので、2回に分けます。
WEB制作者が気になる記事はこちら
2014/09/03
デザインという仕事は、いろんなことに詳しくなっていきます。相手先の商品・サービスのこと、企業の背景のことまでもよく知らなければ、良い成果物ができないからです。このへんが、同じ作る仕事といえども、技術系のシステム職務の人と圧倒的に違うところになるんでしょうか。営業・マーケティングという職…
2014/08/29
レスポンシブデザインで作る場合のメリットとデメリットは? という問いもよく聞くようになったので、整理してみます。相対的に考えるために、レスポンシブではない作りとして(WEBデザイナー上の)「アダプティブデザイン」という概念も併せて比較していきます。WEB業界でのアダプティブデザインの概念のひ…
2014/06/20
少し前にブログにアップロードする画像の形式について質問されたので、初心者向きの説明。JPG とか GIF とか、いろいろある画像形式をどれにするか、それぞれどう使い分けるか。写真や絵などの画像は、無圧縮なデータの状態(BMP(ビットマップ))であると仮定して。それをあらゆる方向からブログ用(WEB用)…
2014/05/29
最近は、jQuery の普及もあって、手軽にスクリプトが実装できる良い時代になりましたね。技術革命によって大量生産品の「モノ」が普及した、かっての時代のような感覚をも覚えます。これからはプログラムの世界であっても職人のような存在は消えていき、オープンソースを利用した二次産業のような作り方になって…
















 at 2014年10月08日 19:19
at 2014年10月08日 19:19